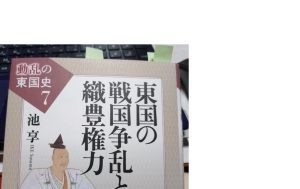半分くらいまで読んだ感想。細かいところ。
まずは通年売ってくれないかなというのがありました。シリーズで通史にするから前の本持ってないと微妙に分からなくなって、全部のシリーズをまとめて売ってくれないかな上杉博物館、と思った。専門家じゃないから「ご存知の通り」的な話についていけない悲しみ。単純にお前が馬鹿だから?そうだね、わりといつも通り!
それはいいのですが、まだ全体を通して読んでいないので、細かな部分のざっくりとした感想。というか書ける部分がやっぱり地元の寺や神社の権力と、一般庶民の生活の部分が大きいですね。
東国は何だかんだ前書きにもありましたが蝦夷というかそれなりに荒れた土地、京や奈良の都に比べて野蛮的な解釈がないでもないのですが、鎌倉幕府、関東管領などからそれなりに広大な土地もそうだし、プラスしてそれなりに文化的に発展していたから余計面倒だった部分はあるよね、というか。
その分、撰銭とかもろにやらかしているのがその土地や地方でそれぞれ違うから、一つの通貨や桝などの大きさ、そういったところから整えていこうとしないと全域の掌握は無理なんですよね。そうなると北条も今川も上杉も武田も死ぬほど苦労するし、戦の他に各地からの租税やそういったところを理解しないとそれぞれ民というよりは土地が着いてこない、というのは難しい問題点だなあと感じました。
だから、結城氏の「結城氏新法度」の部分はコラムまで面白かったです(54P 二-1「頻発する紛争」あたりから)。東国でもこういった法度、全国的には、というか歴史的には「御成敗式目」などが有名ですがこういったものは東国でも伊達、武田なども作っているんですよねぇ……紛争の内容も撰銭から商売、酒の席の件まで、武士も領民も訴え出方から何まできっちり制度化する、この制度化するという部分が戦国時代が「戦国」とついてもどうやって治めていくかの過渡期ではあったというか、過渡期というよりここが基礎になった部分は大きいような気がします。
あと個人的に。
・相模一宮寒川神社。ここは当たり前のようにあるけれど、当たり前のように難しい神社なんだよなぁと改めて思った。米沢上杉にも蘇民将来のモチーフとして五芒星は残っていますが、何だろうね、どちらかというと一宮でありながら東国、それも渡来の方向性が違う神社の可能性が高いというのはどこかで指摘されていますね。シベリヤ系かアラビア系、とにかくそっちの方向の発音に近いのですよね。アラビア語かペルシア系の発音に近いものが多かった記憶。アラビア語と古代アラビア語とペルシア語は共通点が多いので省略しますが、古代アラビア語とアラビア語を分けて考えるの疲れたから放置
・曹洞宗の発展。この部分ですが、この本だけだと「ほー」みたいな内容になるのですが、道元は特に経済的なことを意識しなかったので発展しなかったというよりはそこまで権力的な加護を受けられなかったんですね。門徒が少ないからそもそも受けなくても十分なくらいの宗教集団だったのもありますが。現世利益的なものをあまり深く考えなかったのもありますが。高野や比叡には劣るのですよね、禅宗がいくら好まれてもやはり「これ」というのがないので。で、本の中でも語られましたが瑩山の頃にいろいろ工夫して民衆受けのするものを作っていくわけですが、別に両祖として対立等は一切ないものの、未だに永平寺と総持寺ではイメージが違いますね。山奥か否かもそれはあるのですが、どちらも本山として寺によってはどちらの宗紋(家紋みたいに使うもの)を使うところも多いですが、単純明快に総持寺の方が町場から行きやすいし観光客が多い。永平寺は行こうと思って次の日いける場所にはないのとどちらかというと観光には力をいれていないかな、という感じ。それでも権力的な加護を受けるには臨済宗にも及ばなかったんですけどね!結果的に生き残ったからいいんじゃないかな(ルシフェル)。