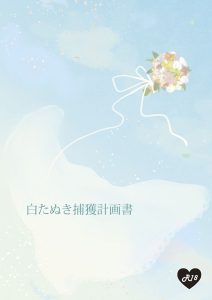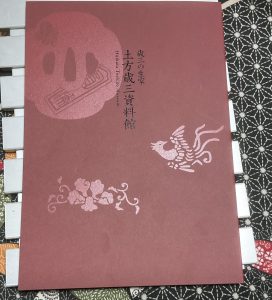文字認識のこともあり、読んだものを日記に付けています。今日はやっと1Q84BOOK2まで再読終わったから感想。
10年以上振りくらいに読んで、BOOK2まで、というか書き下ろしのBOOK3をなにかの拍子にもらったから再読しました。
話の筋立ても結末も細部も何もかも忘れていて、読む速度も例のことで遅く、しかし忘れていたからとても楽しく入り込んで読んで、19章あたりで『全部意図的に忘れた』ことを思い出した。
私はこの物語に耐えられなかった。あまりにも面白くて、楽しくて、それなのにあまりにも破綻していて、惨くて。
いつも思うが、なぜ村上春樹はあんなに綺麗で面白くて楽しい文体で、あそこまで陰惨な、ヒトの傷、あくまで暗部ではなく、誰かが抱え込んで自覚すらしていない傷を抉り出すような文章が書けるのだろう。すごく好きだけれど、あんなに美しく傷口を描写するのが全世界で受け容れられる意味が未だに分からないです(もちろん嫌味ではなく純粋な疑問ですし、私も好きな一人なので何も言えない立場ですが)。
BOOK3を読めば救われるのかと思ったけれど、少なくともBOOK2までの時点で青豆と天吾は救われている。作品としてだけれど救われているし、それは作者も意図していたと思う。
ふかえりもある種救われているんだよ、こんなにもいびつに。
システム、大いなる天蓋、神、天、父、世界を貫く鉄の法則、宇宙の原理法則とか、共産主義、コミュニズム、資本主義とか、宗教も哲学とかの学問も、化学や数学、文学も、今までもこれからも、過去も現在も未来も、ある意味で一つの正解や蓋然性を担保する意味的なものを要求して追求する。
それを文学的に「父」と呼ぶしその最も簡便な点は「父がこう言ったから世界はこうなった」という論理だと思う。それは「神がこう言ったから」「原理がこうだから」「システムがこうだから」という形で私たちの社会一般で普通に使われるが、その発想は父権制イデオロギーとかそういうのと紙一重というか、父というか神というか法則というかシステムというか、ある一点に責任と担保を求めるのは、それがマルクシズムだろうとコミュニズムだろうと共産主義だろうと資本主義だろうと民主主義だろうと宗教だろうと科学だろうと「父権制イデオロギー」だろうよ、と思う。拡大解釈ですが。
1Q84はある意味で「父権制イデオロギー、あるいは父そのものに対するトラウマの克服」というか、そういう、ある意味で反文学的な話かもしれないですね。たくさんの世界中の作品はシステムの中でシステムそのものの話や父ってかシステムや法則への挑戦とか、そういうやつですが、これは「父からの傷がまずあり、父抜き、システム抜きの世界の構築」という途方もない話だと思います。
まず父(システム、親)に主人公の青豆、天吾は傷つけられ、棄てられる。ふかえりは父を棄てた、ように見える。
しかし3人とも「私が今こういう人間になったのは、親のせいだ」と説明する、もしくは親から与えられた傷が深すぎて説明しきれない。
じゃあそっからなんかシステム抜きの、父権制イデオロギー抜きの穏やかな意味での世界を勝ち取る物語か? とワクワクして読むじゃん。最後まで読むじゃん。
絶望的な、だけれど確かな救いが三人に与えられて、当時の書評を読むと「父抜きの世界」とか「バッドエンド」とか「システムを超越」とかアルベール・カミュの「神もシステムも十分に信じていません」を引いているのとかあるけど、違うじゃんという確かな絶望しか感じないのは私が馬鹿だからだろうか。
青豆はふかえりの父、つまり現在最も世界のシステムの要の人物を殺すことで、システムの側の主要人物になる。しかも、青豆自身は宗教システムによって人生を破壊されながら、宗教システムの教祖を殺し、そちら側に深く関わる主要人物になる。
天吾は父に棄てられ、自身の中にやっと「父というシステムと物語」を消しされたところで、今度は天吾自身が「父というシステムと物語」を書きはじめ、彼自身が「父になる」。
ふかえりは「父という宗教システム」から逃げ切り天吾に助けられたが、父が喪われた後に、「天吾という新たなシステム上の父を作り上げる」。
この物語は父やシステムから受けた傷を曝露し、さらけ出し、癒したあとに、その父やシステムと訣別して、あるいは破壊して、そうしてから、そうしたからこそ、ゆっくりと彼ら彼女ら自身がその代替システムとして組み込まれていく途方もないグロテスクさを感じます。
私が馬鹿だから読み違えていて、全員が父から離脱出来ているのかもしれないけれど、私には彼ら彼女らが代替システムとして組み込まれていく途方もないグロテスクさしか感じられない。
当たり前だけど世代じゃないから書物や歴史としてしか知らないけど、1Q84でも語られる安保闘争が第二次世界大戦敗戦からの地続きの精神的な学生の闘争だったと分析されることがあるように、どんな理念や考えがあっても、傷があっても、結果的に代替手段でしかなかったように。