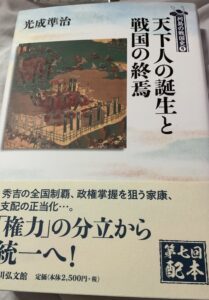改めて読んでもこの本は本当に面白くて、没入出来て、一気に読むことは出来なくなってしまったけれど、とても夢中になって読んでいた。
それくらい楽しかったけれど、後に残るのはどうやったって痛みだけで、book3のラストまで読んでも何一つの充足感ももたらさない。ここまでの痛みを伴う話しか書かない、書けない村上春樹という作者は本当に凄いと思う。
技術論的なものは私には書けないし、中身の考察は成され切っているだろうから、個人的なこと。
私がこの本で最初から最後まで一番引っ掛かって、一番怖かったし、一番の原因だと思っているのは、どうやっても「ふかえり」だった。
ふかえりは何もしない。だけれど、この一連の「1Q84年」で起こったことの全ての原因は彼女だと思うし、全てが彼女から始まっていると思う。始まっているのはそうなんだろう、空気さなぎのことからそうだろうし、リトル・ピープルの声を聴くものであり、ドウタを生み出すマザの大元なのだから。
だけれど物語後半から「声を聴くもの」を「さきがけ」は必要としだし、それは「リーダー」だったことになる。あくまで「ふかえり」ではない、と。リトル・ピープルが必要としたのはふかえりだったはずだった。リーダーというか、深田保、深田絵里子の父は、娘の特性を知り、その声を翻訳する役だったからリーダーになった筈だったのが、そのリーダーが死んだ途端、その間にあったこと、穏田の言うことを信じるなら様々な流れがあって、リーダーは「リトル・ピープル」の声を聴けなくなった≒翻訳できなくなったから、ふかえりは既にマザではなく、だから既に「さきがけ」は天吾とふかえりから興味を失い、新たに「声を聴くもの」を受胎した青豆を「確保」し、おそらくは「マザ」となった青豆をも確保することに専心していた。
でもこれ、本当だろうか? 絶対という言葉はあまり好きではないから絶対ではないが、だいぶ違うと思う。
まず、ふかえりは「猫の町から帰ってきた天吾は御祓いをしなければならない」から、という理由から天吾と性交渉を持ち、「私は妊娠しない」という自身の中にある意味で「つばさ」と同じ「ドウタ」のような性質を示すが、それは違っていた。実際にふかえりではないが、その結果として「ふかえりではなく青豆が天吾の子供を受胎した」。「その時にリーダーは死んだ」。
恐らくふかえりはその結果を知っており、自身という「マザの大元」であり、つまるところは神の巫女、リトル・ピープルの巫女である存在として「マリアの処女懐胎と同じものを青豆に授けた」。「処女懐胎の父親は天吾である」。「二人は1984年に帰った」。「少なくともそこは1Q84年ではない」。「そこで『ちいさなもの』は慈しまれ、生まれるのだろう」。
私はこれに恐怖を覚える。
なぜか。ふかえりはほとんどすべてのことを見通しており、リトル・ピープルの善悪を示さず、それを良いとも悪いとも言わなかった。悪ではないし善ではない。それを以てだろう、父であり、教団さきがけのリーダーである深田保は、やはり「善悪の定義以前から我々と共にあるもの、存在しているもの」とリトル・ピープルを定義した。
そうしてふかえりは牛河のことを見通しており、知っていながらカメラに目を向け、「私たちは見られている」と天吾に警告したが、その時に既に牛河の最期を予見していた。最期を予見していなくとも、少なくとも彼女は牛河を見て、牛河に視線を送った。彼を知覚していた。でなければ「憐れむような視線」を彼にするだろうか? それは純粋な憐憫だったと見ることもできる。侮蔑でなく、無関心でなく、憎悪でなく、愛情でなく、憐憫。牛河という存在そのものに対する憐憫。そうであればそれは余計に性質が悪い。自分自身を肯定しえないものに対する憐憫。それは上位存在に与えられた特権だろうし、それを無意識的にせよ、意識的にせよ行うふかえりという少女は、まさに「マザ」、神の巫女であり、リトル・ピープルの同胞であり、ギリヤーク人の考えるところの森の人であると思う。
だからこそ、天吾との性交渉は彼女の意思であるとしか思えず、もっとさかのぼれば空気さなぎを天吾に書き直すことを『許した』ことも、青豆の存在を知覚していたことも、『空気さなぎ』の出版によって父、というよりは自身が巫女として仕える神の声を伝える者が死ぬことも、『青豆が新たなマザで巫女になり、その存在を生むこと』も、『天吾がそれを造りだし、その巫女の新たな神になることも』すべて織り込み済み、というよりは、既に神と巫女である自分の声を伝える者がそろそろ役に立たなくなるから、新たな代役を立てねばらならないことを考えたうえで、『空気さなぎ』を戎野先生の娘に語り、ずっとその機をうかがっていたから彼女はリトル・ピープル、及びその神に許されていたのだろうとさえ思う。
私にはこの1Q84という物語が「ふかえり」が自身の父、自身の巫女としての神の声を伝える者の限界を察知して、新たな伝道者を造りだすための物語に見えた。それは20年前に「天吾」と「青豆」が出会った時から巧妙に仕掛けられた罠であるように感じた。その時から周到に、二人を出会わせて、二人をアダムとイヴ以上に、ナザレのイエスと聖母マリア以上に、天吾を神とし、青豆を処女懐胎させ、新たな「神と世界を作り直す」のがふかえりの物語であり、それは「月が二つある世界を書き出した小説」で以て天吾に引き継がれ、「処女受胎し、天吾との子供を妊娠した」青豆によって引き継がれて、月が二つある1Q84年から月が一つの(今のところ)現実の1984年を侵食し始める。
二人は世界から抜け出したように見えて、ふかえりとその父によって新たな世界に送り出され、新たな世界を侵食し、新世界の神になるだけだと思う。
もっと言うならば二人の親がNHK集金人や証人会、さらに牛河の系譜、田丸の系譜、戎野と深田の学生闘争、その更に以前、そんな近代のことではなく、深田保が言うように、「善悪の定義以前から我々と共にあるもの、存在しているもの」、太古から文明とかそういう以前に人間の存在が自我を持った時点で「宗教」という存在証明を求めてしまった時点まで遡ることが出来る罠かもしれない、とさえ言えるほどに。それほどまでに深く、二人は「いずれ世界を支配し、侵食し、深田絵里子という巫女と、その声を聴く彼女の父が作り出した神の世界を広げる者になるだろう」。
私には「1Q84」はそういう物語に見えました。村上春樹の書く小説にしてはずいぶん趣が違うな、と。Book2までならまだそこから「死」とか「苦しみ」という形で逃げ切ることも出来た中で、Book3まで描ききることで、結果的にその物語が収束した場所はそういうシステマチックな部分だったのではないかなあと思うと同時に、このような物語を書く村上春樹というのはどういうことだったのだろう、という稚拙な考察を置いておきます。考察といっても私の脳の許す範囲&ネタバレというよりは他の様々な意見を入れたくないので、あくまでも私の感想です。後でウィキペディア先生と新聞の過去の書評欄くらいは読みたいですね。
村上春樹は繰り返し「システム抜きの世界」「神抜きの世界」「父抜きの世界」という「父権制イデオロギーの否定」というものを長らく題材にしてきたように思います。スピーチ「卵と壁」は有名になりましたが、あれは「システムというのは遠大なものだし、その中でどう振舞うか」というような話でした。でも「1Q84」を読むとそれは少し違う視点で見るしかないようなものに思えます。
「私は哲学者ではない。私は理性もシステムも十分には信じていない。私が知りたいのはどう振舞うべきかだ。より厳密に言えば、神も理性も信じないでなお、どのように振る舞い得るかを知りたい」(1965年 アルベール・カミュのインタビューの一部抄訳)
Book2まで読んだ時に、掻い摘んで読んだ書評にカミュのこれを引いているものがあったと書きました。「卵と壁」時点で、村上春樹はまさにこのカミュの「理性もシステムも神も信じていない状態で、どのように振る舞い得るか」というものを目指して、その一つの答えが「卵の側に立つ」ということだったのだろうと思います。それはその時までに書かれた作品に共通していたテーマでしたし、何よりこの作品でもBook2のラストに青豆が拳銃自殺しようとし、実際にその時点ではBook2のラストを読む限りでは脳天を貫いて終わったように読める、その時点では実行されたことでした。青豆は「卵の側」の存在として「システムという壁」にぶつけられ、もしくはぶつかり、無惨に文字通り破裂する。卵という存在はシステムという壁の前ではこれほどまでに無力であるが、青豆は確かに「システムの側のリーダーを殺害し、またそれによって天吾を救出した。そうしてシステムのほころびを衝いた」という点において、物語の執筆者としての村上さんは「卵の側」に立っていた。それはカミュが言うように「どのように振舞い得るか」という答えを示したということです。青豆は最後に誓いの言葉を叫ぶ。それは空言でした。だからこそ、「何も信じないままに、それでも世界の中でどう生きるか」という課題を克服した、はずだった。だけれど物語はそこで終わらなかった。
終わらせることが出来なかった、と私には思える。終わらせることが許されなかった。
ここからは推測です。実際に村上春樹さんが考えていることや、この本を書くにあたってのことは知りません。一読者でしかなく、上に書いた通り、これから当時のインタビューや書評を図書館などで仕入れたいと思っています。また、Wikipediaやwebで分かるところまでは調べたいですが、今はまだ自分で出来る範囲でアウトプットしたいので何も調べていないので、間違っているところは気にしないでね。
この本に出てくるいくつかの問題点を整理するにあたって、この物語を書くにあたって、村上春樹は「システム抜きの世界」「理性」「救済」「信仰」「殺人」「戦争」「神」「男女」というあたりのことについて、ある意味で「それは無理だ」という結論に達したのではないでしょうか。確か1Q84は日本では爆発的に売れましたが、海外の評価は話が回りくどいとかでいまいちだったと記憶しています。それはそうだろうと最後まで読んで改めて感じました。それはそうだ。この回りくどく繰り返される言葉の端々にある「申し訳ないけれども」死んでもらう、戦ってもらう、神になってもらう、助けてもらう、書いてもらう、住ませてもらう、生きてもらう、あらゆる「申し訳ないけれども」という修辞が、なんというかこれ、日本人にしか響かないから。日本人というか、なんだろう、ごく狭い地域にしか響かない気がしましたが、それでも書かずにはいられなかったのだろうなあ、と。それは世界性をもった文学ではないというか、もっと単純に村上春樹自身が書きたかっただけな気がします。
で、ここからは更に推測。歴史的事実や、村上春樹の今まで取材してきた事象(事件)や、『物語の中の』歴史的背景を含めて考察していますが、あくまでも「1Q84を書くにあたって、こんなことがあったのではないかな」という考察です。
そこには私の歴史認識も関係ないですし、更に言えば、実際の歴史も、この本で語られることも関係なく、むしろ「1Q84年」「月が二つある世界」という特異な場所と現実、非現実のファンタジーを書くにあたって起こったことへの考察です。
あんまり気にしないでね☆彡
1、1984年という60年代安保闘争と70年代安保闘争の記憶
2、新興宗教(オウムもそうだがエホバやそれに類する「終末論」を含むもの)
3、神とシステムと父と天上の方
このあたりかなあ。加えて「アンダーグラウンド」でも村上春樹は「オウム真理教」を扱っていますが、それよりも更に深化していったのがこの本だったような気がする。その宗教に対して、というよりはもっと表層的な部分になっているように思えますけども。村上春樹のオウムのテロルに対する取材の話は有名ですし、この本にも関わるのでしょうが、オウムの話はいろいろ面倒なのでしません。すみません。
1、安保闘争
前にも十二国記の感想で書きましたが、私は本当に世代ではないので、学生安保闘争については記録や書籍、或いは人から聞いたことがある、というくらいでしか知りません、本当に70年代安保の時に20歳で東大生の人が単純計算で今70代ということになりますからね。60年代安保とかもう訳分からんよ。調べて研究未満のことはしていますから少しは喋れる、程度と思ってね。ということですが、今回の「1Q84」にも深く関わるのではないかなあと思います。東大の安田講堂だの、総理官邸前一斉検挙だのがありましたが、それはこの本にも確かに出てきて、その学生闘争の指導的立場にあった生き残りが戎野先生であり、その友人である深田保であり、そうして片方は学者として生きていき、片方は山梨の山間部にコミューンを形成していく。歯車が狂ったのは深田の娘、絵里子、後の「ふかえり」が戎野のところに逃げてきた時だった。その結果として出版された『空気さなぎ』がコミューンの闇を暴いていき……とこの本の中心的な問題なのですが、安保闘争のことは本当に最初期に戎野先生から深田家のこと、さきがけとあけぼののことを語る時に僅かに語られるだけで、流されてしまいます。
ですが、これがこの本の主軸であるように思えるのです。なぜでしょうね。
思うに今の70~ギリ50代くらいの作家、文科系の作家にとって学生闘争は避けて通れない部分ではあるのではないかなあと思います。小野不由美、高橋源一郎、村上春樹、赤川次郎……枚挙にいとまがないですね。
脱線しますが、小野不由美の「十二国記 月の影 影の海」で語られる学生闘争に関係する部分は本当に数ページ、直接的な描写は数行、一ページに満たないと思います。「壁落人」は学生闘争のさなかに異世界に紛れ込んで、そこで生きている。終わり。
だけれども、その描き方はあまりにも冷たい。「帰りたいと思わなかったのか」という問いに「新天地に来られたことが嬉しかった、時代に倦んでいた」と壁は答える。それはまさしく学生闘争のぐちゃぐちゃな感情だと思います。そうして「せめて門まで日本の話をしましょうか?」という問いに「必要ありません。そこは私が革命に失敗して逃げてきた国です」という一言のあとには何の説明もなく、次の章が始まり壁の出番はその後一切ない。
東大の安田講堂、革命に失敗、時代に倦んでいた、この辺りの断片的な情報から壁は学生闘争に参加し、そのさなかに十二国のある異世界に紛れ込んで定住した、と予測は出来ますが、小野不由美の筆致はそこだけが切り取られたようにあまりにも冷たいと感じます。責めるでもなく、称賛するでもなく、ただ冷たい。
ただ、陽子という異世界の国の王になるべくして連れてこられた少女にとって、新たな国を作ること、国を治める王になること、国を捨てて帰るのか、帰らないのか。剣を持って戦うのか、戦わないのか、というものを突き付ける時に壁落人という、安保闘争、革命、国から「逃げて」その異世界の国に流れ着いた存在を小野不由美は書かずにはいられなかったのだろうなあと思います。ライトノベルという括りのファンタジー作品であえて書くこともなかったのかもしれないのに。
1Q84の中でも語られた学生闘争に話を戻せば、というか、小野不由美の描いたこれが全てで、この考え方が全ての根底にあるのだろう、と思わせるようなものが「1Q84」の根底にもある気がしました。
「学生たちや、先導し、先導した指導者たちは時代に倦んでいた」が「その革命は失敗した」し、「多くの者は責任を取らず逃げ出した」。そうして「その革命というのがなんであったのか、今になっても誰にも説明できない」という。
学生闘争は日本の中の東大とかそういう上澄みとまでは言わないですけどもインテリジェンス層の学生やら研究者やらそういった人たちが主導しての、派閥もいくつかありましたがざっくり言えばマルクシズムでした。共産主義。でもあの状況でアカになる意味はないし、その後の展望なんてどこにもなかった、と思う。
何度か書いているけどもね、マルクシズム、コミュニズムが機能しえたのはそれを提唱したマルクスやエンゲルスが「ブルジョア階級」だったからです。彼らは決して「プロレタリア」ではなかった。そうだというのに「プロレタリアを解放せよ」と言った。そうして近代日本や現代日本ではコミュニズムを共産主義、と訳したし、それを赤と全世界的に呼ぶし、極右(時代によってもしくは極左、これ本当に極端でよく分からない部分はありますね)と呼ばれる政治思想になりましたが、正式な訳語は本来的に「共同体主義」とか「共有主義」というもののように感じます。私はそこまでドイツ語に通じている訳ではありませんが、少なくともコミュニズムと言われて「共産主義」とか大戦時のドイツやらイタリアやら日本やらの帝国主義やナチズム、現代の中国の「共産主義」に通じるところを感じるものは一切ありません。「共同体主義」とか「共有主義」と訳すべきだと思うし、一般的な「コミューン」とか「コモン」から派生した言葉であればそうであるはずだったと思います。だって単純にキリスト教系の教会とかの前にある「住民の共有地」のことを「コモン」と呼ぶわけですからね。私有地じゃなくてそこは共有地ですよーっていうところを「コモン」とか「コミューン」と呼び、それは主義とか主張とか政治思想以前に、もっと単純明快に住民単位の共有地、村の公民館みたいなもんです。公民館っていうと管理者が市区町村になるから更に違ってきて、村とかそういうんで共同で管理するなんかそういう共有の場所です。空地みたいな、村の祭するとこみたいな。それが共産主義になるかい、訳したやつは馬鹿なんじゃないかと思います、別段、マルクスにもエンゲルスにも思想的に共鳴するものは一切ありませんが、訳語としては言語的な意味で馬鹿なんじゃないかと思います(馬鹿はひさめさんだよ)。
で、世界史の授業とかにもあった気がしますが、「囲い込み」が始まって「共有地(コモン)」から追い出された人々がプロレタリア(労働階級、小作人)となり、それを富裕層であるブルジョアが使役するのは間違っている、とマルクスやエンゲルスはぶち上げて、「本来この共有地、及び共有地から得られる財産は彼らプロレタリアのものであるから、プロレタリア、労働者を解放せよ」ということになったわけです。ざっくり。歴史的な背景は抜きにすると、ですが。
これがプロレタリアから発せられたものだったとしたら「私たちの居場所を返せ」という返還要求を呑む者は誰もいなかったでしょうが、実際に奪った側のマルクス達が「彼らに返さなければならない」と言い出したらそれは聞かなきゃならないことだった。だって実際やったことだから、そこには理性やら罪悪感やら、真っ当な感性があれば何となくでもそういう気分になるから。
マルクスの社会主義が大きく受け入れられたのはそういう点が大きかったと思います。あくまでもマルクスは奪う側だった。
ですが、そういうマルクス主義やコミュニズムは第二次世界大戦を境に、というよりは「共産主義の悪用」によって大きく衰退します。衰退という言い方が適切かは知りませんが、少なくとも資本主義経済は立てなおされ、グローバリズムが進み、社会主義的、共産主義的観念は悪とされました。その可否はよく知りませんというか、今現在、私は資本主義経済に生きていて、社会主義経済には生きていません。アンチグローバリズムがどうとか、資本主義の限界とか、いろいろありますが、『今現在』という修辞をつける限り、資本主義じゃないでしょうか。マルクスは資本主義を終わらせて社会主義に移行することを説き、それが受け容れられましたが、それは二度の大戦によって倫理的にも論理的にも瓦解した。
にもかかわらず、日本で60年代と70年代に起こった学生闘争の支柱はマルクス主義でした。
この歪みの恐ろしさというか、特に70年代闘争の方の大学生は大戦を知らない年代です。敗戦後に生まれて、敗戦は知っているが、戦争は知らない世代。そういう世代になぜかマルクスが合致し、そうして流血と死者を伴う闘争は起こった。それは一方的な暴力ではなく、当時の方から聞いただけの話ですが過激派の身内が過激派の身内を殺すことも珍しくはなかったとか。思想が合わない、それだけの理由だったそうです。
部外者だから言いますけども、上に書いた通り、彼らにマルクス主義が扱えるはずがなかったと思います。その頃の学生は「敗戦によって奪われた側」であって「敗戦によって失われた国土や政治的空白を私たちに返せ」と言っているのであって、その後のプランがあったとは思えないからです。それはマルクスの考えた出来合いの社会制度や主義主張ではなく、自分たちで考えた社会制度を持って来なければならない部分だったのだろうと思います。
小野不由美が「十二国記」で指摘していた通りに「そこは私が革命に失敗して逃げてきた国」です。壁落人に革命を成すことは出来なかった。なぜなら彼らは奪われた側ではあっても持っていた側ではないから。ならばもっと違う、マルクス社会主義ではない社会制度を以てではなくては革命は成せなかった。だから流血があった。それに気づかなかったから壁落人は「全く社会制度の違う異国」である「十二国」で暮らすことが出来たし、帰ることを望まない、と。だから同時に、異国に流されて王になることを強要されたように見える陽子は、王になるべくしての冒険譚と成長物語でありながら「日本」と「十二国」の社会制度の違い、思想の違い、宗教の違いを丹念に書いていくし、それはある意味で延王尚隆が言う通り「破綻のない理想的過ぎる社会制度」です。もしかしたら小野不由美の考える「理想的な社会制度」なのかもしれませんが、これは赤川次郎氏の指摘ですが「十二国で上手くいっている国は少ししかなく、どこも内乱かなんかで荒れている」のが現状だから、人が考えた大体の制度は結局破綻すると小野不由美さんは考えているのかもしれません。
1Q84も結局は同じだと思います。違うのは、その革命に失敗した後に戎野にも深田にも逃げ場は日本という国以外になかった。だから戎野は穏当に学者になったが、深田は「全く違う社会制度を打ち立てた」。その社会制度は「ふかえり」という巫女の誕生によって完成します。その巫女「ふかえり」の誕生は、社会制度であり「社会システム」を構築し、破壊し、そうして再構築してあらゆる世界に波及し蔓延させていくとても制度の高いシステム構造だと思います。
疲れたからここまで。